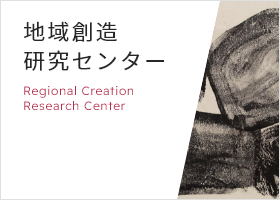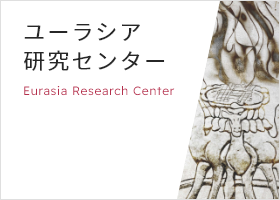出前講義のテーマと内容(カ~サ行の教員)
| 講義タイトル | 概要 | 講師 |
|---|---|---|
| 地域をつなぐ国際協力 | 「子どもには幸せになって欲しくて勉強させるが、遠くの学校に行かせたら帰ってこない。帰ってきても仕事がない。どうしたらいい?」日本の国際協力NGOが活動するインドのある村の村長さんの言葉です。それぞれの国には異なる課題がありますが、同時に国境を越えて共通する課題も存在します。よりよい社会づくりに向けて、お互いに学び合う国際協力のあり方を考えます。 | 亀山 恵理子 教授 |
| インドネシア語を学んでみよう | 人口2億7000万人を抱える東南アジア最大の国、インドネシア。多様な民族が暮らすこの国には、さまざまな言語や文化がみられます。多民族国家であるインドネシアで公用語として広く普及しているのがインドネシア語です。講義では、インドネシア語での簡単な挨拶や自己紹介を学ぶとともに、インドネシアの文化?社会についても紹介します。 | 亀山 恵理子 教授 |
| グローバル化時代における異文化理解とは? | 戦争、貧困、性別や人種にもとづく差別、宗教間の対立など、現代世界は多くの問題に直面しています。いずれも異なる「文化」が衝突して生じる問題です。本講義では、私たちが普段からなにげなく使用する「〇〇文化」という言葉が、実は「他者」との共存を妨げる要因になっていることを知ったうえで、グローバル化時代における異文化理解のあり方を考えてみたいと思います。 | 窪田 暁 教授 |
| 「スポーツ移民」から現代社会を読み解く | 1990年代以降、欧米のプロ?スポーツ界を中心にアフリカ?中南米出身の外国人選手の活躍が目立つようになりました。この「スポーツ移民」とよばれる人びとが誕生する背景には、急速に拡大するグローバル化の影響があり、プロ?スポーツ界も安価な人材を発展途上国に求めはじめたことが要因としてあげられます。本講義では、サッカーやプロ野球、日本の大相撲などさまざまなスポーツでみられる「スポーツ移民」に注目することで、グローバル化する現代社会について考えてみたいと思います。 | 窪田 暁 教授 |
| アメリカ文学の今 | アメリカ文学といえば、何を思い浮かべるでしょうか?フォークナーやヘミングウェイ、フィッツジェラルドを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、現在のアメリカ文学は多様化し、アジア系にラテン系、もちろんアフリカ系など世界のあらゆる地域にルーツを持つ作家が活躍しています。この講義では多様な移民作家の作品を紹介することで、多様化する現代社会について再考します。 | 桑原 拓也 准教授 |
| 英語文学を味わう | 現代は情報化が進み、あらゆる物事が高速化しています。その一方で、着実で堅実な思考も求められています。この講義では、日本に住む人々にとって、身近ですが距離を感じる英語を、時間をかけて丁寧に読んでいきます。現代の英語文学の冒頭を単語レベルにこだわって読むことで、速い思考の基礎となる「スロー」な思考のあり方について考えていきます。 | 桑原 拓也 准教授 |
| ヒトは血管から老いる | 血管は全身に分布して、栄養や酸素を運ぶ通路となっています。健康の維持には、血管を知り、血管を健全な状態で維持することが大切です。 最新の医学研究の知見を交え、生活習慣病と血管の関係をお伝えします。血管を健やかに保つためには、どのようなことに気をつけるべきか考えてみましょう。 |
小山 晃英 准教授 |
| 超高齢社会における都市の地域コミュニティとは? | わが国では超高齢社会?人口減少社会に突入しているが、これからの人口変化は都市部で大きく現れ、従来の地縁や血縁に依拠する様々な取り組みでは対応できない課題が増大するものと思われる。そこで、今後、都市の高齢化?人口減少などの変化について問題を提起し、それをもとに、地域コミュニティとして考え、取り組んでいかなければならないことは何か、事例紹介を含めて皆さんとともに考察する。 | 佐藤 由美 教授 |
| 多機関?多職種の連携による居住支援 | 変化の大きな社会において、自分の力で住まいを確保できない人たちが増えている。そうした人たちの居住の安定を確保するためには、行政と民間、住宅?福祉部局や専門機関、不動産事業者、サービス事業者等多くの機関や職種の人たちが協議し、連携することが求められている。そうした課題に対応した先進事例を紹介しつつ、各地域の特性に応じた取組み方について考えていく。 | 佐藤 由美 教授 |
| タグチメソッド-日本が生み出した世界で活用されている最適化法- | タグチメソッドは田口玄一博士が体系化した様々な問題に対して適用されて効果を上げている最適化の方法です。その適用範囲は製造業における品質管理に始まり、企業組織の最適化や釣果の予測など非常に広く、世界中で利用されています。本講義ではタグチメソッドの発展の歴史などを紹介し、その数理について簡単に解説します。また品質管理だけではなくユニークな適用例について紹介します。 | 鈴木 新 教授 |
| 脈波で何が分かるのか? | 手首に指を当てて、心拍数を測定した経験がある人は多いと思います。ここで測定される振動を波形にしたものが脈波であり、心拍数以外にも、その硬さ、リズムなどを知ることができます。これらの脈波から得られる情報から分かる心身の状態は多く、例えばストレス、血圧、酸素飽和度(コロナウイルスでも利用されました)などがあります。本講義では脈波の測定原理からその利用方法までを紹介します。 | 鈴木 新 教授 |